シンプルな映像が魅惑的なマノエル・ド・オリヴェイラ監督最新作『A Talking Picture(英題)』完成披露試写会&記者会見!

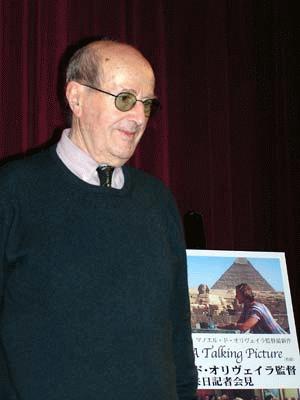


2001年7月、7歳の少女マリア=ジョアナは母親のローザ=マリアと一緒に、インドのボンベイにいるパイロットである父親に会うために船旅に出発した。歴史の教授であるローザ=マリアは、これまで本の中で知らなかった世界をその目で確かめたかったのだ…。
ポルトガルの巨匠マノエル・ド・オリヴェイラ監督の最新作『A Talking Picture(英題)』は、母子の辿る悠久の時空を超えるかのような旅を通じ西洋文明について語った作品で、今年度のヴェネツィア国際映画祭での上映でも大喝采を持って迎えられた。
本作の撮影時94歳、それでも年1本のペースで作品をコンスタントに発表し続けているオリヴィエラ監督が、小津安二郎生誕100年シンポジウムへの参加が決定し、撮影中の最新作の撮影の合間をぬって来日を果たし、12月10日東京日仏学院2階エスパス・イマージュにて開催された『A Talking Picture(英題)』の完成披露試写会に出席、またひき続き記者会見も開催された。
オリヴェイラ監督は、公文書上は小津安二郎と同じく12月12日、そして実際は12月11日が誕生日ということで、会見の翌日には95歳の誕生日を迎えられる。「(日本で誕生日を迎えられるのは)とても嬉しい。でもそれ以上に皆さんが、今日ここに集まってくださったことを嬉しく思います。今回は偶然こちらで誕生日を迎えましたが、日本は今回が初めてではないし、最後にもならないと思います」。そう挨拶されたオリヴェイラ監督は、矍鑠としたという表現が失礼ではないかと思えるほど、若々しく元気と気力に満ち溢れている。オリヴェイラ監督とは旧知の中であり、「40年以上若さと映画への愛が持続されている方」と語った高野悦子氏の話によれば、その秘訣はご本人曰く「フィルムを食べているからね(笑)」ということである(毎日ではないそうだが…笑)。
『A Talking Picture』のテーマは、先に書いた通り西洋文明。では、何故今回このテーマを監督は選ばれたのだろうか?「西洋文明は、これまである一定の道を進んでいたように思うのですが、9月11日のテロ以降別の道に進みだしたようです。これはおそらく、これまで続いてきた西洋文明に終止符をうつ恐ろしいことではなかったかと。この事実が、私を西洋文明とは何かという考えに至らしめさせたんです。今まで西洋文明が進んできた路線が変わったことで、諸国は、今の状態からどう抜け出すべきかと別の方策を探らなければならない。そういうことがいいたかったんです」(オリヴィエラ監督)。本作で描かれる豊かな文明を巡る旅。そんな旅が迎える終着点を観ると、監督の意図はずっしりと観客に響いてくるだろう。ロードショー公開時には、この言葉を思い出しながら、観る者それぞれで作品を受け止めてみよう。
本作で印象深いのは、撮影はほとんどフィックスで行われ、ひじょうにシンプルに語られているということだ。カメラが目まぐるしく動き回る昨今の作品に慣れ親しんだ者にとってこの映像体験は魅惑的であり、かつ逆に刺激的であるかもしれない。「映画作りで最も難しいのは、シンプルさを表現していくことなんです。文章にしても、様々なことを言いたい時に長い文章を書くことは誰でもできるが、ごく短い文章で語るのは難しい。現在は様々なことが盛り沢山でバラエティに富み、スペクタクラルなものが観客をひきつけていますが、そうした類の作品はドラッグのようなものではないかと思うんです。映画はドラッグではなく、アートでなくてはならない。観ている観客が、感情だけでは無く理性も納得させる作品でなければならないのです。そのためには、シンプルでゆったりしたテンポでなければならず、そこでは観客が積極的に参加できると考えていますし、それが一番大事なことです。観客はそれを受動的にではなく、能動的に観ることが出来るのです。派手なものに人は振り向くかもしれませんが、そこには深さはなく観客が観るには値しない。そうではなく観た人にそれ以上のものを与え、観た人それぞれの考えを加えていけるような作品であって欲しいと思うのです。そのためのシンプルさなんですよ。昔、映画とはもっと素直なものでしたが、今は中毒のようなものになってしまいこれでは駄目だと思うのです。人間は考える理性の動物だから、理性の動物が向えるような作品でこそありたいのです」(オリヴィエラ監督)。
なお、『A Talking Picture』は、2004年日比谷シンテ・シネにてロードショー公開!感覚のみならず理性に訴えかける作品を、皆さんそれぞれで体験して欲しい。
(宮田晴夫)
□作品紹介
A Talking Picture(英題)